競技で優れた成績を収めるトップアスリートは、多くの国民が拍手喝采を送るスーパーヒーローだ。しかし、引退のそのときまで、競技一筋に打ち込んできたようなアスリートには、思うようにその後の職が見つからないなど、試練が待っていることも多い。それは社会問題であるとの認識のもと、トップアスリートのセカンドキャリアを支援するプロジェクトを進めてきたのが、筑波大学大学院人間総合科学研究科の菊幸一教授だ。日本のスポーツ界で起きている問題の本質は、どこにあるのだろうか。
トップアスリートといえども
多くは引退と同時に職と支援の基盤を失う

オリンピックでメダルを獲得したり、プロスポーツ界で活躍したりするようなトップアスリートは、広く国民から注目を集めるヒーローである。しかし、どのような種目でも、生涯現役を続けることはほとんど不可能だ。多くは20~40代の間にファーストキャリア(現役生活)を引退し、セカンドキャリアを歩むことになる。このとき、スポーツ社会学の研究テーマとなるような大きな問題が起きると、菊幸一教授は言う。
「アスリート、なかでもファーストキャリアを競技一筋で、2020年の東京オリンピックを目指して打ち込んできたようなトップアスリートは、引退と同時に、職の基盤、あるいは支援の基盤を失ってしまう可能性が大きい。そのために、スポーツパフォーマンスに頼らない次の生活基盤を獲得するにはどうすればよいのか、という問題が生じるのです」
もちろん、セカンドキャリアの問題は日本に限るものではないが、ヨーロッパやアメリカには、程度の違いはあっても、有効性のあるセーフティネットが設けられている。「クラブ型」のサブシステムを取っているヨーロッパでは、高等教育進学へのキャリアパスが中等教育資格修了試験によって狭くなっている――平たく言えば、アスリートとしての能力だけでは進学できないため、国家を代表するトップアスリートの受け皿は、国家が準備する公務員職であることが多い。引退後のセカンドキャリアは、そこから3~5年の猶予期間を設けてカリキュラム化され、保障されるチャンスが与えられるのだ。また、「学校型」のサブシステムをとっているアメリカでは、NCAA(全米大学体育協会)による厳格なトップアスリートに対する奨学金制度の適用と大学全体の卒業率向上方策によって、安定したセカンドキャリアへと進みやすくしている。

「日本をヨーロッパ型にしようとすれば、トップアスリートを生みだす仕組みの構造改革が必要です。なぜなら、日本の競技スポーツは学校の運動部がベースになっているからです。水泳や体操、サッカーといった種目を除くと、競技は学校の運動部が基盤になっています。しかも、学力は問わないというかたちで進学させていますから、ヨーロッパ型にはできません。だからといって、アメリカの真似もできないのです。大学が、ほとんど学力は問わずに卒業させてしまいますから」
かつての日本は、企業がトップアスリートの受け皿になっていた。その仕組みが崩れたことにより、セカンドキャリアの問題は一気に顕在化したのである。
「日本では、スポーツ推薦で、あまり学力を身につけずに大学まで行ってしまうケースが多いのです。1980年代までは、大学を卒業したアスリートを体育会系と呼び、十把一絡げで企業が採用していました。あるいは、企業スポーツというかたちでアスリートを支えていたのです。しかし、1990年代以降、グローバル化のなかで、日本企業が世界と戦わなければいけなくなると、体育会系の能力だけでは通用しなくなりました」
2020年の東京オリンピック以降
問題は深刻化する恐れがある
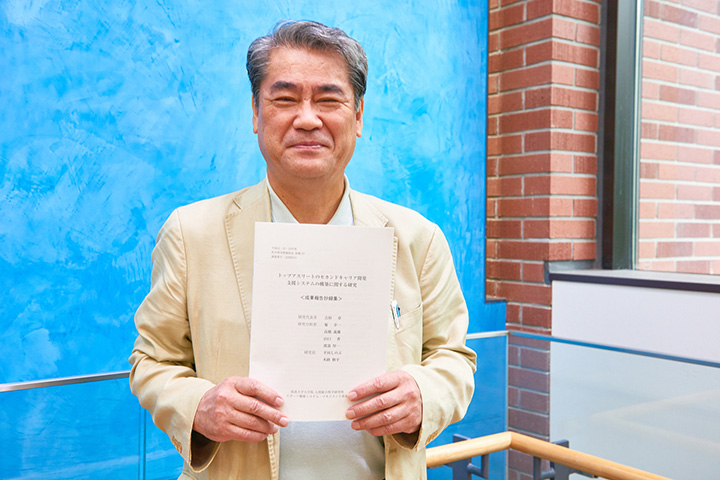
菊教授が、当時の専攻長である佐伯年詩雄教授らとともに専攻全体の取組みとして「トップアスリートのセカンドキャリア支援教育のためのカリキュラム開発」というタイトルの研究を、文部科学省の特別教育研究経費を用いてスタートさせたのは2005年のことだ。セカンドキャリアの問題が、大多数の国民の目には触れない状態で、大きくなっていた時期である。そして、2010年には、教育プログラムだけではなく、支援システムの構築など、環境づくりもテーマに含めた「トップアスリートのセカンドキャリア開発支援システムの構築に関する研究」と題したプロジェクト研究に着手している。
「国、企業、学校、そして、アスリート自身が考え方を変えないと、日本のセカンドキャリアの問題は解決しません。私自身は、ジュニア期の競技者に対する対策が重要であり、アスリート自身もジュニアの時代からセカンドキャリアを意識してほしいと思いますが、現実的には難しいでしょう。日本では、中学校、高校の段階で全国大会が数多く開催され、そこで成績を出せというプレッシャーがものすごく大きいのです。なおかつ、その成績によって大学まで自動的に進めてしまうという仕組みがある限りは、状況は変わらないと思います」
現時点で、「トップアスリートのセカンドキャリア開発支援システムの構築に関する研究」は、アスリートを救済するまでには至っていない。しかし、インターネットなどを通じて、国民がこの研究を知り、セカンドキャリアの問題が社会問題であると認識されることが重要なのだ。

2005年にスタートした「トップアスリートのセカンドキャリア支援教育のためのカリキュラム開発」では、3年間にわたり報告を行った。
「アメリカも現在でこそ、NCAAの活動などによって、状況は改善されてきましたが、1980年代あたりをピークに、セカンドキャリアの問題は深刻だったのです。たとえば、アフリカ系アメリカ人のアスリートはフットボールや野球などでプロに引っ張られることを狙い、大学に進学するのですが、プロとして活躍できるのは一握りです。卒業せずに中途でプロに入っても、活躍できなければセカンドキャリアが始まります。しかし、一般社会で活躍できるスキルは身につけていませんから、まともな職業につけないのです。この問題は“social death”と呼ばれるようになりました。個人の問題ではなく、これは人種差別の問題であり、貧困の問題も絡んでいるという考え方からきた言葉です」
アメリカの状況は改善されてきたが、日本の状況は、このままでは悪くなる一方と考えられる。
「危惧しているのは、2020年の東京オリンピック以降です。たくさんの若者が、夢を追いかけましょうということで、東京オリンピックを目標にしています。話題性のあるアスリートであれば、メディアも追いかけますから、一躍、時の人になることもあるでしょう。しかし、現実問題として、オリンピックのようなイベントは花火と同じで、打ち上がったあとは消えてしまいます。社会は、アスリートの養成に走るだけでなく、何らかの策を講じておく必要があるのです」
アスリートのセカンドキャリア問題は
すべての人に関わる普遍的なテーマ

セカンドキャリアの問題を解決、あるいは改善する方策は、まったくないのだろうか。
「人材派遣会社のような商業ベースの組織が、アスリートと企業を結びつける活動をすれば有効かもしれません。スペインで調査をしたときに、印象的なことがありました。人材派遣会社が、あるプロバスケットボールのチームに所属していたメンバーを企業に売り込んだのですが、セールスポイントは選手としての成績ではありませんでした。素晴らしいチームに所属していたメンバーという点をアピールしたのです。そのチームは1位になるような強豪ではありませんでしたが、絶対に反則をしないことで知られていました。小学校や中学校の生徒たちの模範になるような試合をするチームだったのです。人材派遣会社は企業に対して、こういうチームの一員を社員にすれば、企業イメージがよくなるはずだと売り込んだのです。私は、アスリートを成績ではなく、人間として評価する、こういう橋渡しのやり方があるのかと、非常に感心しました」
菊教授は、企業は今後、パラアスリートの支援にも力を入れていくべきだと考えている。
「日本も国を挙げてパラアスリートの養成をしているので、障がい者スポーツの世界でもセカンドキャリアの問題が生じることになるでしょう。多くの企業が2020年の東京パラリンピックに向けてパラアスリートを支援していますが、それが終わったら、企業がパラアスリートをどのように扱うのかは、注視していかなければいけません。企業には、障がい者スポーツが発信するメッセージを受け取り、パラアスリートを末永く支援することで、企業のイメージを高めるという姿勢をとってほしいと思います」
セカンドキャリアの問題は、実は、アスリートだけのものではない。私たち一人ひとりの問題でもあるのだ。
「人間は、死ぬまで、ステージごとに発揮できる力を備えています。多くの人は、自分が最高のレベルにいたときのことをイメージしてしまいがちです。しかし、人間の発育発達のピークは青少年期ですから、年を重ねればそのピークから離れていく一方なのです。比較の対象がひとつのピークしかないと、いつまでたっても幸せにはなれません。何かのピークが過ぎたとしても、次のステージで活躍すればいいのです。このことは、トップアスリートのセカンドキャリアの問題と通じています。いまできることは何なのかを考え、精一杯やることです」
多くの人が、まだ気づいていない、トップアスリートのセカンドキャリアの問題。しかし、それは普遍性のあるものなのだ。そうであるのなら、菊教授のプロジェクト研究は、思いのほか、汎用性のあるものなのではないだろうか。
菊幸一(Koichi Kiku)
1957年、富山県生まれ。教育学博士。九州大学健康科学センター講師、奈良女子大学文学部助教授を経て、現在、筑波大学大学院人間総合科学研究科スポーツ健康システム・マネジメント専攻教授。著書に『近代プロ・スポーツの歴史社会学』(不昧堂出版/1988年)、『「からだ」の社会学』(世界思想社/2008年)、『よくわかるスポーツ文化論』(ミネルヴァ書房/2012年)など。モットーは「探究心を忘れない」こと。


















































