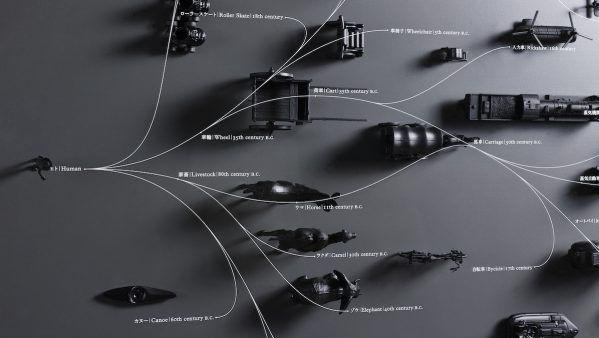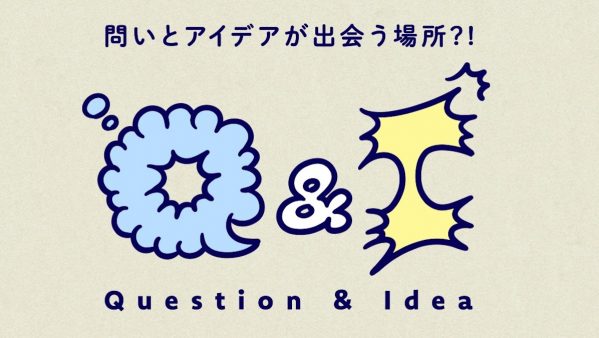それはまさに「転ばぬ先の杖」―。 今年1月4日から9日にかけて、ラスベガスで開かれた世界最大級の見本市「CES(コンシューマエレクトロニクスショー)」。ここで注目を集めていたのが、転倒したら家族へ自動で警報が送られる未来の杖「Smart Cane」です。
Smart Caneは一見すると普通の杖ですが、グリップの部分に「dring」と名付けられたアラートシステムが埋め込まれています。これは2013年設立のフランスの企業Nov’in社が開発したもの。Nov’in社は人工知能やデータ分析、製品接続などの分野で高い技術を持ち、安全や健康に関するアプリケーション製品のPlug&Playソリューションとしてdringアラートシステムを生み出しました。
 dringアラートシステムは充電可能で長寿命のバッテリーを搭載しているうえ、小さくて軽いのでさまざまな製品に埋め込んで応用可能です。具体的には加速度計やジャイロスコープなど複数のモーションセンサーによって物体の加速度や傾き、方向などを検出。データを携帯電話網で送信し、GPSによる位置情報も参照します。サーバーに集積されたデータはAI(人工知能)が処理し、それぞれのユーザーの行動パターンや癖などを記録。データは厳重に管理されており、安全な方法で送受信されています。
dringアラートシステムは充電可能で長寿命のバッテリーを搭載しているうえ、小さくて軽いのでさまざまな製品に埋め込んで応用可能です。具体的には加速度計やジャイロスコープなど複数のモーションセンサーによって物体の加速度や傾き、方向などを検出。データを携帯電話網で送信し、GPSによる位置情報も参照します。サーバーに集積されたデータはAI(人工知能)が処理し、それぞれのユーザーの行動パターンや癖などを記録。データは厳重に管理されており、安全な方法で送受信されています。
ほかにも靴に埋め込んだ製品例がありますが、Smart Caneの場合は利用者が転倒すれば、自動で家族に電話したり、テキストメッセージやEメールの送信をしたりして警告を知らせます。警告は家族が確認するまで連続して送られ、確認が取れたことは利用者にも通知されるので安心です。

Smart Caneを作るFayet社は1909年創業で、“生きた遺産”にも名を連ねるフランス最後の杖メーカー。軽量、頑丈、かつ人間工学に基づいて体にフィットする美しい杖は老舗ならではで、dringアラートシステムはグリップ部分に違和感なく埋め込まれています。製品化にあたっては、パリのデザインスタジオ「Pineau & Le Porcher(ピノ&ルポルシェ)」ともコラボレーションしました。
Fayet、Nov’in両社にとって大きな挑戦だった、という「未来の杖」は、CESのイノベーション・アワード・プログラムで入賞。大きな評価を受け、来場者の注目を集めました。Ismaël Meïté氏と共にNov’in社を創業したVincent Gauchard氏は、「転倒することによって外出する自信を失い、食事に出かけたり、友人に会ったり、ということもしたくなくなる人がいます。この気持ちの負のスパイラルを断ち切り、高齢者が安心して外出できるためのツールとしてSmart Caneを開発しました。Smart Caneを使っていれば、転倒したときに家族や介護者に情報が伝わり、助けに来てくれることを知っているだけで、自信を持って外出できるようになるでしょう」と言います。また、「歩行頻度や活動量など、すべての歩行データを集約・分析することにより、機能の衰えなどの予測にもつなげられます。この情報をもとに、医師から適切な指導を受ける、といったことにも応用できるのです」と話し、まさに先進技術を利用した「未来の杖」であることをうかがわせました。
Smart Caneは2017年末、フランス国内やヨーロッパで販売開始予定。日本でも2018年末の取り扱いスタートを目指し、さまざまな確認を進めている最中だそうです。
問い合わせは、Nov’in社の問い合わせ窓口:infos@novin.fr.まで。
http://dring.io/en/the-connected-cane/