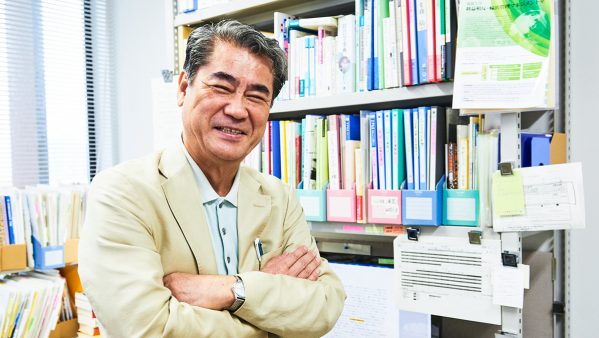日本における子どもの死亡原因の統計、あまり知られていないのだが、いつも上位にくるのが事故による死亡だ。高所からの転落など、子どもの思わぬ行動が死亡につながるケースは少なくない。子どもにとっての本当の安全とは何か、センシングを使い導き出そうとする動きが出てきている。これまでの常識を疑い、センシング技術で子どもの安全性向上に取り組む東京工業大学の西田佳史教授は、「親が『目を離してはいけない』から『目を離してもいい』環境へとパラダイムシフトする」と話す。いったいどういうことなのか。自分事化をきっかけに描く一歩先の未来とは? 編集長・杉原行里が訪ねた。
子どもが生まれたことを
きっかけに研究をスタート
保護者の見守りの限界
杉原:今日はよろしくお願いします。早速ですが、西田教授がセンシング技術を使って子どもの安全性向上の分野を研究しようと思われたきっかけは?
西田:単純ですよ、子どもが生まれたからです(笑)。当時、福祉工学という分野はありましたが、主に高齢者が対象で、子どもの安全に寄与するものはなかったんです。例えばISO(国際標準化機構)やJIS(日本産業規格)の定義は「受け入れることのできない危険がないこと」ですが、やっぱり危険はある。危険がないことと定義するのではなくて、危険を扱える能力を備えた状態の社会に変えていきたいと思ったんです。
特に子どもの事故は、身体の機能変化と非常に関わりが深いと思っています。身体はもちろん、認知機能や運動能力が急速に発達する時期なので、昨日できなかったことが今日できるようになる。でも事故が起こるとまず、子どもから目を離した保護者の見守り責任が問われる。しかしその事故原因の多くは、そもそも我々が設計した環境やデザインが生み出してしまっているのです。そこで、デザインによって変えられる可能性があるんじゃないかなと考えたんです。

怪我をしにくい環境はできると語る西田教授
杉原:最近、電気ケトルで火傷をした子どもの話を聞いたばかりです。なぜそんな危険なデザイン構造になっているのか疑問を感じていたところです。
西田:そうなんです。人間の注意力に頼る「見守り」だけで事故を防ぐことはできない。それを証明するためには、実際の生活の場で起こり得る現象を切り離さず、計測をして理解するということが必要でした。そこで、子どもの実際の行動を画像処理して、子どもの転倒時間や、電気ケトルが倒れて熱湯がもれ広がるのにかかる時間、物が落ちたり倒れたりする時間を測定しました。子どもが転倒するのにかかる時間は平均0.5秒。これは、例え1メートルという至近距離で見守っていたとしても、人間の見守り能力に頼るだけで防ぐにはどうしても難しい。
また例えば、子どもが歯磨きをしながら動き回って転んで怪我をしてしまうという事故も多発しています。いくら「止まって磨きなさい!」と親が言っても、言うことを聞いてくれる子どもばかりではない。見守りだけでは不十分だから、事故が後を絶たないと僕は思っています。
杉原:本当にそうで、保護者の見守りだけで事故を防ぐには限界がありますよね。親がどれだけ注意していても、子どもってじっとしていられない。
西田:そうなんです。さらに我々は怪我のデータを統計的に処理するために、まずは病院の協力を得て子どもが怪我をした部位のデータを集めて可視化しました。ビッグデータを元に効果として結果を出すことができるようになったんです。例えば、歯ブラシの事故では、目を離さないで見守ることに限界があるなら、目を離してもいい環境・デザインをつくろうではないかと、私が「ABC理論」と呼んでいる、Ⓐ変えたいもの、Ⓑ変えられないもの、Ⓒ変えられるもののなかで、Ⓒの“変えられるもの”として、転倒データを元に歯ブラシのデザインを変えることができたんです。

研究室にはベビーベットやベビーサークルなど、実際に家庭で使う家具などが並んでいる。
杉原:そうだったんですか。最近は曲がる歯ブラシが販売されていますよね。規格化は考えられていないのですか?
西田:いい質問ですね。歯ブラシに限らず、最初はとにかく問題を提示することが大事だと考えているんです。そこから企業との共同研究がはじまって、プロダクトが出来上がる。そしてそれをユーザー側が魅力的なモノ、価値あるモノだと捉えることで他のメーカーが参入して常識化されていく。この段階まできたら規格化してもいいんじゃないかと。このサイクルを、データに基づいてやれるといいなと思っているんです。
最近は、転落事故について研究しています。最近は子どもの登る姿勢のデータベースが作れるようになってきているんです。どういうことかと言うと、子どもがどこを、どんなふうに登る可能性があるかということが分かることで、転落事故防止につながります。身体機能や認知機能の変化が大きい1~2歳の子どものデータを中心に集めていますが、今後は保育園の遊具で観察するとか、現場からの情報を集められるような仕組みが出来るといいなと思っています。
子どもから目を離してもいい環境の整備
杉原:なるほど。子どもの1~2年って変化がとても大きい。このアルゴリズムがディープラーニングしていくことも大事で、そこから得られるデータから環境やデザインを変えていくことによって、大きな事故を防ぐことが出来るようになるということですよね。

西田:その通りです。我々が研究を続けてきたなかで気が付いたことは、社会が必ずしも問題を理解しているというわけではないということ。リサーチして問題を抽出しなくてはいけない場合もある。我々が子どもの事故について取り上げたのが2007年で、それまではそういった活動はなかったんです。そこで、子どもにとって安全なもの、いいものをアイコン化して推奨することで市場を拡大していけたらと、2007年に「キッズデザイン賞」を作りました。ニーズがイノベーションに返還されるという仕組みが出来上がりつつあるのかなと思っています。やはりいいものを褒めていかないと社会はシフトしない。
杉原:素晴らしいですね。確かにハードパワーとしての規格も必要ですが、エンジニアリングでもデザインを変えられるものがきちんと評価されなければユーザーも育たない。アイデア自体はかなり前からあったのに、実装としてのフィールドになかなか到達しなかったということですよね。おそらく倫理的な問題もあるかと思います。今は、一般社会におけるデータの扱い方についての理解が深まってきている。
西田:そうですよね。現場で役に立つ知識の作り方が、IoTの時代で変わってきたのかなと感じています。家庭においても、新しいスマート環境を作っていくということが出来る時代になってきたのではないかなと。社会側の受け入れ方が変わってきたと思うんです。最近はZoomやSkypeで家の中まで入っていける時代になってきたので、画像認識を使えば、その家、その人に合わせた安全対策の提案が出来るようになりますよね。
杉原:確かに。事故の可能性が可視化されることで、よりイメージしやすいし、事故防止につながると思います。事故に様々な外的要因があったとしても、誰にでも必ず起こる可能性がある。高齢化の問題で考えると自分事化しやすいですよね。いまや3人にひとりが高齢者と言われる時代になっていて、家族にひとりは高齢者がいるという社会ですから。
西田:そうなんです。日本の人口分布と事故の確率をグラフで見てみると、人口分布は平たんな一方、事故の確率は生まれた瞬間と65歳以上に多い、いわゆる「バスタブ曲線」です。人生には妊娠・出産や介護したりされたりと、どこかで必ず変化がある。この変化に対応していかないといけないのが現代。変化するところに色々なニーズが隠れている。つまり、 “常識を疑え”ということなんです。これまでの常識だった「事故を防ぐために目を離すな」から、我々が目指しているところは「目を離してもいい環境」を作ること。それを認めていく環境を作ること。怪我を許容する自立支援や、リスク管理型の社会参加を促す方向にもっていきたい。

杉原:謎解きのようなグラフですね。こんなにも課題の抽出されている社会に生きているってラッキーですよね。これからいろんなことにチャレンジできる。
西田:そうですね。このメッセージが若い世代の人たちにどんどん伝わっていくといいですよね。我々には解かなくてはいけない問題がたくさんある。まだまだ未熟な社会です。人生100年時代と言われているいま、子どもからお年寄りまで、“機能が変わる人”にフォーカスして、その変化にどう対応していくかが問われる社会になってきているわけです。
西田佳史(にしだ・よしふみ)
東京工業大学 工学院 機械系教授。1998年東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻博士課程修了。博士(工学)。同年4月通産省(現経産省)工業技術院電子技術総合研究所入所。2003年産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター研究員。同年、同研究センター人間行動理解チーム長。2005年〜2012年科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業(CREST)研究代表者。2009年産業技術総合研究所デジタルヒューマン工学研究センター生活・社会機能デザイン研究チーム長。2013年同研究所デジタルヒューマン工学研究センター首席研究員。2014年から2019年東京理科大学連携大学院客員教授。2015年産業技術総合研究所人工知能研究センター首席研究員。2017年より、セコム科学技術振興財団の特定領域研究助成(社会技術分野)の領域代表者。 2019年より産業技術総合研究所人工知能研究センター招聘研究員。2019年から東京工業大学工学院機械系教授に就任。