ピョンチャンパラリンピック開幕直前の3月3日に21歳の誕生日を迎えたばかりのチェアスキーヤー村岡桃佳選手。アルペンスキー女子大回転座位で5位入賞した14年ソチ大会を経て、17年W杯白馬大会の女子スーパー大回転座位で優勝、18年ジャパンパラ大会の女子大回転座位で優勝するなど、めきめきと実力を伸ばし、2度目となるパラリンピックでのメダル獲得に期待が高まる。RDS社のクリエイティブ・ディレクターとして、村岡選手のチェアスキー開発を手掛けてきたHERO X編集長・杉原行里(あんり)は、プロダクト開発のエキスパートとしてはもちろんのこと、時に、若きエースの相談役となり、悩んだ時には、人生の先輩として、厳しくも温かいエールを送るべく指南するなど、アスリートとサプライヤーとして以上に、多角的な信頼関係を築いてきた。そんな杉原にだからこそ、村岡選手が見せたくれたアスリートの素顔をぜひご覧いただきたい。
“ド真ん中”を一発的中させた、
驚異の身体感覚

杉原行里(以下、杉原):二つのフレームを使い分けている日本人選手って、桃佳以外にいるの?
村岡桃佳選手(以下、村岡):現状では、いないと思います。果たして、それが良いか悪いかは分からないのですが、フレームは、日進医療器さんに作っていただいたトリノモデルがベースの高速系と、ソチモデルをベースにした技術系(※2)の2種類をレースによって乗り換えています。
杉原:桃佳の背骨って、片側にすごく曲がっているから、背シートは、他の選手とはちょっと形状が違うんだよね。座シートがポジションの要であるのに対し、背シートは、ターンする時に力の入る部分だから、フレキシビリティが極めて重要。軽量化を図りつつ、考え方を少し変えて、開発を進めてきたけど、フォースプレートを使って、桃佳の重心度を測った時は、本当に驚いた。さすがですよね。4歳の頃から車いすに乗っているからなのか、ポジションが完璧だったから。
村岡:あの時は、自分が一番びっくりしました。骨や身長が伸びる成長期も、ずっと車いすで過ごしてきたので、姿勢の崩れなどで、骨が変形してしまっていて、今、そのまま固まっている状態です。普通に座っている時、重心は片方に寄ってしまっているんですけど、こちらで測っていただいた時、これだけ体が歪んでいるのに、チェアスキーに乗った時だけは、なぜか、すごくきれいに“ド・センター”でした。
※2 技術系=チェアスキーの技術系種目のこと。スラローム(回転)、ジャイアントスラローム(大回転)、スーパーコンビ(スーパー複合)の3種目がある。
静かに燃える勝ちたい気持ち

杉原:セッティングに関して、桃佳は、自分の感覚をほぼ100%信じて良いと思う。データとして、結果に表れているから、何かがおかしいと思った時は、その感覚を頼りにセッティングを変えられるよね。その意味では、疑うところをひとつずつ減らせるし、きっとそれは、長い時間を車いすで過ごしてきたからこそ、得られた感覚でもあるよね。
今のところ、ポジションが完璧だった理由については、まだ解明できていなくて。その意味でも、桃佳は、まだ僕たちが知らない未知の部分が多い選手だなと思う。ひょっとして、バランスボールに乗ったら、めちゃくちゃ上手いんじゃない?
村岡:今度、乗ってみましょうか(笑)。
杉原:でも、桃佳のマシンは、まだフェーズ1か2くらいかな。大輝くん(森井大輝選手)が、4~5年かけて、改良に改良を重ねた末に、フェーズ10とか15まで行っているので、これからどんな風に進化していくか、楽しみだよね。今は学生だけど、2022年の北京大会では、社会人として就職しているだろうから、そこを背負っていかないといけないし、モチベーションも今とは違ってくると思う。桃佳にいつも「これが最後だよ」と冗談で言ってるけど(笑)、今回のピョンチャン大会は、学生の桃佳と一緒に迎える最後のパラリンピックになる。ピョンチャン大会の意気込みは?どんな気持ちで臨むの?
村岡:逆に、何も考えずに挑みたいです。ただ、自分の中では、今まで以上に、“勝ちたい”という気持ちが芽生えていることは確かです。
杉原:気負わずにね。気負う時には、僕の顔をできるだけ思い浮かべて(笑)。マシンを壊すことに対しては、僕たちは文句を言わないけど、逆に、中途半端な滑りをしてきたら、怒るので覚悟しててね。うちの基準は、「面白いか、面白くないか」なので。でも仮に、金メダルを獲ったとしても、心配性の桃佳のことだから、ピョンチャン以降もずっと心配し続けるんでしょ?この後、どうしようって。
村岡:今、心配しかないです。マシンが一番のお守りです。
チェアスキーの次世代を担う期待の星
 杉原:今後、応援してくれる人たちには、どんなところを見て欲しい?
杉原:今後、応援してくれる人たちには、どんなところを見て欲しい?
村岡:少し前までの私は、本当にただの甘ったれた大学生でしたが、今こうして、アスリートとして活動させていただく中、気持ちも少しずつ変わってきました。4年前のソチ大会の時に比べると、確かに変わったことも色々とありますが、そんなに強い人間じゃないし、今、本当の意味で、成長している途中だと思います。今後も、楽しみにしていてください。
杉原:チェアスキーの歴史をぜひとも紡いでいって欲しい。切にそう思います。今、男性の先輩選手たちが、黄金期と呼ぶにふさわしい時期を迎えていると思うけど、栄枯盛衰というように、やがて必ず終焉を迎える時が来るだろうから。二十歳の桃佳がけん引していかないと、先輩たちとの間を繋いでいくネクストジェネレーションがいないから、途絶えてしまう。個人的に、チェアスキーって、めちゃくちゃ面白いスポーツだと思っていて。今後は、パラリンピックだけじゃなく、このスポーツの面白さを世の中にもっと広めるためにも、頑張って欲しいと思います。ところで、今日の対談、二十歳の女の子をオッサンがいじめてるみたいになってない?(笑)
村岡:いえいえ、叱咤激励、本当にありがとうございました。
ピョンチャンパラリンピックでは、日本選手団の旗手という大役を務める村岡選手。雪上のハヤブサのごとく、超高速でバーンを疾走する彼女が表彰台に立つ時、それは、世界を驚嘆させると共に、チェアスキーの新たな歴史が幕を開ける鮮烈な瞬間になるだろう。
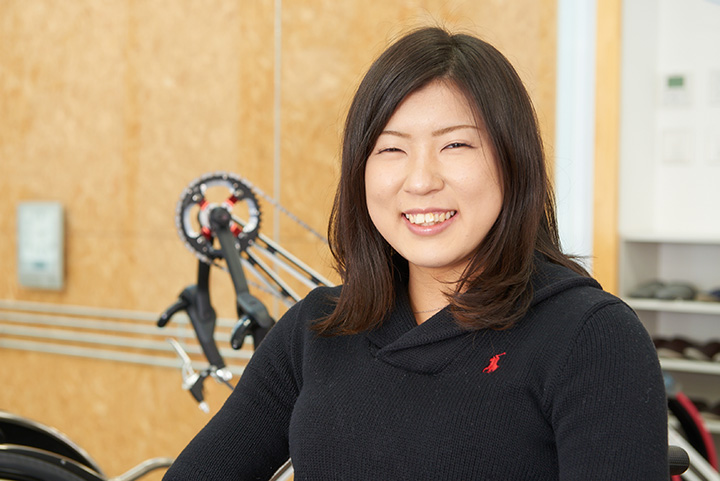
村岡桃佳(Momoka Muraoka)
1997年3月3日生まれ、埼玉県出身。早稲田大学スポーツ科学部3年。4歳の時に横断性脊髄炎を発症し、車いす生活となる。陸上を中心にさまざまなスポーツに挑戦する中、小学2年の時にチェアスキーの体験会に参加。中学2年から競技スキーを志し、本格的にチェアスキーを始める。14年ソチパラリンピックに出場し、アルペンスキー女子大回転座位で5位入賞。17年W杯白馬大会の女子スーパー大回転座位で優勝、同大会の女子大回転座位で3位。18年ジャパンパラ大会の女子大回転座位で優勝。ピョンチャン大会で初の金メダル獲得を狙う。











































