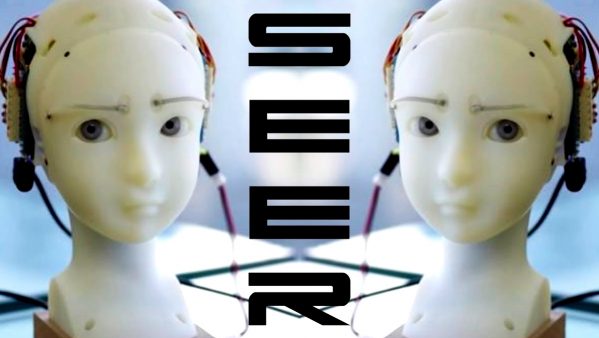昨年開催された、サイボーグ技術の競技会「第1回サイバスロン スイス大会」への参加や、先日、クラウドファンディングで見事目標を達成したプロジェクト「義足の図書館」など、すべての人に動く喜びを与えることを目指し義足を開発する、株式会社Xiborgの代表である遠藤謙さんに、義足の未来についてお話を伺いました。
遠藤さんは、生物の構造や運動を力学的に探求し応用するバイオメカニクスや、リハビリテーション工学、スポーツ工学を専門とし、マサチューセッツ工科大学が出版するTechnical Review誌が選ぶ「35歳以下のイノベーター35人」に選出されるなど、義足開発のエキスパートとして世界的に注目をされています。
 サイバスロンに参加して見えた課題とは
サイバスロンに参加して見えた課題とは
「サイバスロン スイス大会では、“Powered Leg Prosthesis Race”という、大体義足を使用する競技に参加しました。おそらく一般の方がサイバスロンと聞くと、ロボットコンテストのように現場で細かな調整をして本番に挑むようなイメージを持たれると思うのですが、我々がやっているのは、一昨年の段階でリハーサルを始め、本番では工具を一切使わないレベルまで上げ競技に挑んでいるんですね。ですから、チームとしてはすごくいい物ができたと思っています。しかし、いざ競技が始まると、本来の実力が出せなかったことに悔いが残りました。今後の課題は、経験や精神面の強化だと感じています」。 義足の世界では、「どの義足が一番優れているか」というような表現はしないという。なぜなら使用する人に合った物が、その人にとって一番いい義足になるからです。そういう意味では、遠藤さん率いるXiborgチームが作った義足は、間違いなくその選択肢の一つにはなり得る感触はあったと、遠藤さんは確信していました。
 第2回大会で勝つために必要なこととは
第2回大会で勝つために必要なこととは
「製品レベルと研究レベルの義足って、確実に違う物だと思うんですね。そう考えると、我々が作らなくてはいけない物は、確実に製品レベルでなくてはいけないと思っています。正直、現段階では、まだそこに到達していないので、2019年までに着実にこなしていかなくてはいけません。理想はその時点で製品化されていることですね」。
また、陸上のトップアスリートであるジャレッド・ウォレス選手をサポートしているXiborg。「ジャレッドに関しては、サイバスロンとはまったく別視点で契約をしています。それは世界最速を目指しているということです。もちろん彼の能力としてそこを目指せるのはもちろんですが、もう一つテクノロジーが好きであるという点です」。世界最速。分かりやすいだけに、難しい目標であることは誰もがわかること。他の契約選手を見ても目指しているところは一目瞭然です。
「走るってことでも、高く飛ぶってことでもいいんです。一番のポイントは、人間のパフォーマンスを最大限に引き出すことが出来るのは、生身なのかテクノロジーなのかというところにあると思っています。それを考えた時に、現段階で一番分かりやすいのが陸上競技なのです。単純に速いってかっこいいじゃないですか。だからこそ熱くなれるような現象を起こしたいな、という気持ちで研究しています」。
 そして最後に、サイバスロンで使う技術とアスリートの義足で使う技術の違いを聞いてみました。「サイバスロンで使う技術は、日常生活の中での動きに対応する部分が大きいんです。例えば階段の昇降など繊細な動きが出来るか。ただ、先ほども言ったように、そのような動きに関しては、感じ方が個々に違うので評価が難しい所なんです。しかし、最速というところは、もう一点突破で目指すことは一つしかないのが最大の特徴ですね」。
そして最後に、サイバスロンで使う技術とアスリートの義足で使う技術の違いを聞いてみました。「サイバスロンで使う技術は、日常生活の中での動きに対応する部分が大きいんです。例えば階段の昇降など繊細な動きが出来るか。ただ、先ほども言ったように、そのような動きに関しては、感じ方が個々に違うので評価が難しい所なんです。しかし、最速というところは、もう一点突破で目指すことは一つしかないのが最大の特徴ですね」。
今回の遠藤さんにお話しを聞き、強く感じたことが2点ありました。一つは、純粋な情熱を持ち義足というテクノロジーと向き合うことで、人々の夢を背負っているということ。もう一つは、「すべての人に動く喜びを与えること」を実現するためには、彼のような存在が、今、絶対的に必要とされていることでした。これからの彼の活躍に期待しつつ、Vol.2ではHERO X編集長との対談をお届けします。
Xiborgオフィシャルサイト: http://xiborg.jp/