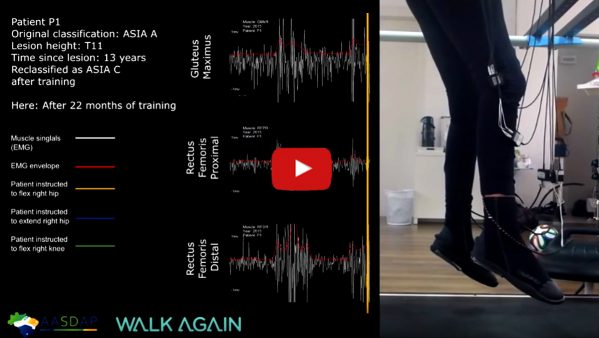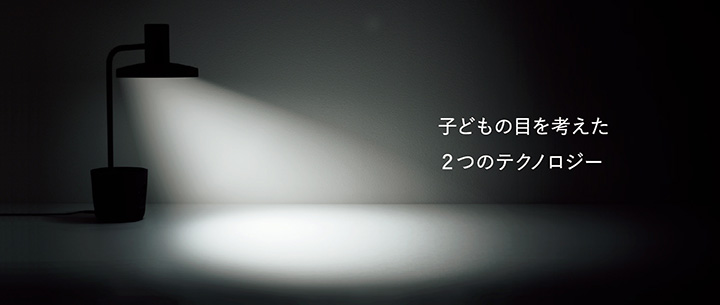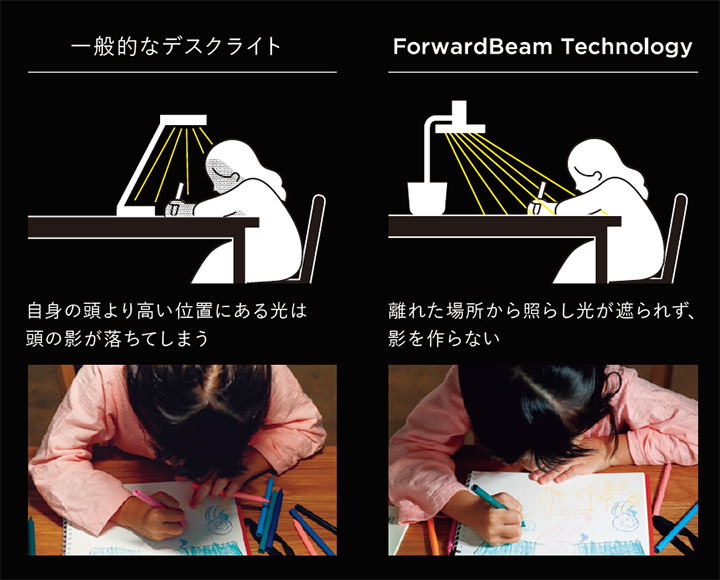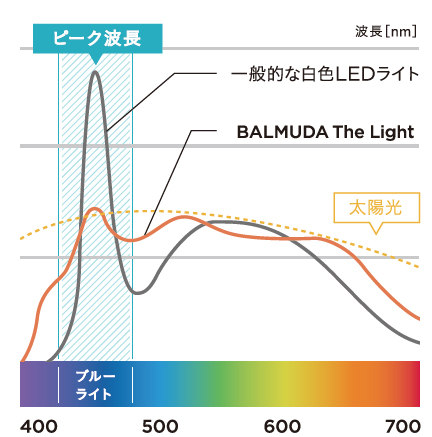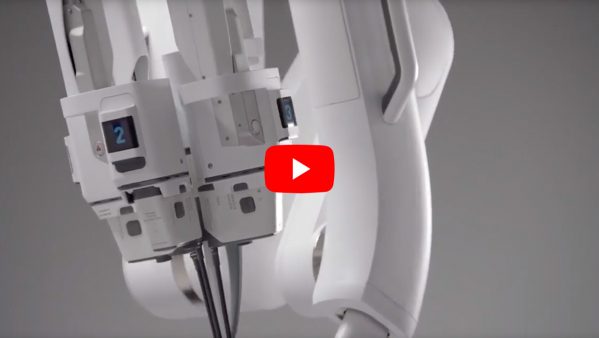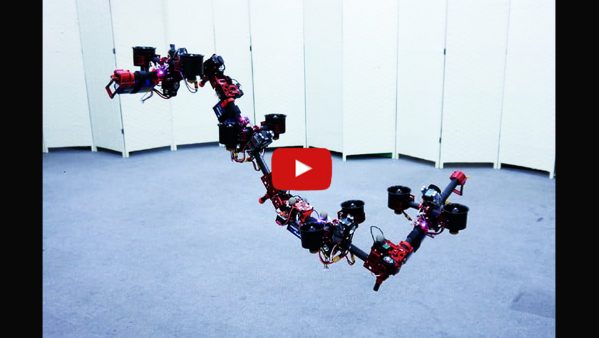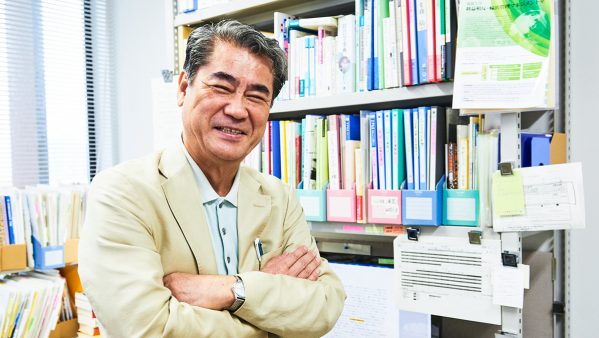ロシア・ノヴォシビルスクで、脳の信号を読み取る操作システムを搭載した車いすが開発された。近年、筋肉を収縮させたり、声の指令などを出すことなく、脳波のみで操作できるモビリティは、様々な企業や研究機関が続々発表しているが、あらゆる可能性を秘めた今回のこのニュースにも、世界から注目が集まっている。日本国内でも、脳信号を活用して外部世界との相互作用を及ぼすブレイン・マシン・インタフェース(BMI)の認知が広まっているだけに、一般ユーザーからの期待値は高まるばかりだ。
神経細胞が生成するインパルスを
コンピュータで命令に変換
ノヴォシビルスクのエンジニア、イバン・ネブゾロフ氏が開発したのは、脳の信号を読み取って、脳波を命令に変換するシステム。それを搭載した車いすは、ユーザーが首から下肢まで麻痺していても、脳が損傷していなければ操作が可能だという。
脳の神経細胞が生成するインパルスをコンピュータで変換することで、前進・後進、ストップ、左・右、ヘッドライトの点灯・消灯、シートの前傾・後傾といった基本的な動きが、座っているだけでスムーズに行える。
日本でも2009年に、トヨタ自動車と理化学研究所が、BMIを搭載した車いすの開発成果を公開し話題になったり、「2017国際ロボット展」では、金沢工業大学がPCと接続した専用ヘッドセットを頭に装着して脳波で操作する車いすを出展したことは、記憶に新しい。脳波を使い、操作性を高めた車いすの開発は、あらゆるアプローチを増やしながら少しずつ前進している。
イバン氏が開発したこの車いすで興味深いのが、無限軌道(キャタピラ)により、急な階段の上り下りや縁石の乗り越えも可能にした点だ。脳波で操作できるだけでなく、高低差のある場所も走行できるようになれば、ユーザーの行動範囲は格段に広がる。いずれにせよ、このプロダクトの今後の動向からは、目が離せなそうだ。
[TOP動画引用元:https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FE2Nw3t4ivE]